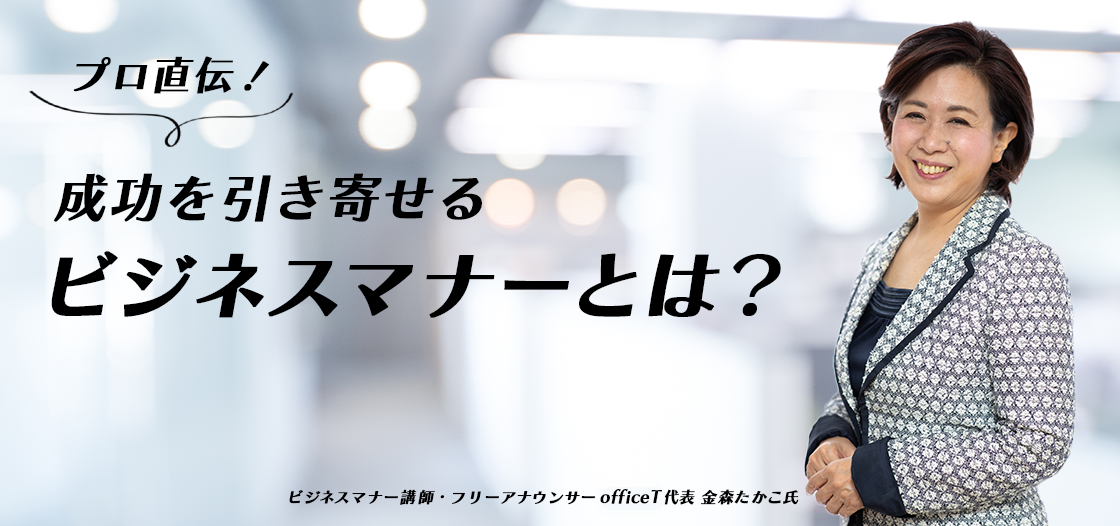 ビジネスマナー講師・フリーアナウンサー officeT代表 金森たかこ氏
ビジネスマナー講師・フリーアナウンサー officeT代表 金森たかこ氏この記事はプロモーションが含まれていることがあります。
ビジネスマナーは、どのように習得して、活用していけばいいのか? そのヒントを教えていただいたのは、ビジネスマナーや話し方の講師で、“言葉・話し方・声・コミュニケーションのプロ”でありフリーアナウンサーとしても活躍する金森たかこ氏。著書も複数出版している金森氏に、新入社員などの若手だけでなく、上司や企業にも役立つ、ビジネスマナーの効果やさまざまなビジネスシーン・カテゴリー別の具体的なポイントなど、「知っているようで知らなかった」ビジネスマナーについてお話を伺った。
目次
- ビジネスマナーは、「金銭が生じる」という点が特徴
- “心をつかむマナー”が仕事を生み、個人や企業、社会を成長させる
- 第一印象以上に大切な、“最後”の終わり方
- ビジネスマナーは堅苦しくない。そこに込められた意味を、まず理解しよう
- どうして、その身だしなみが必要なのか?
- “言葉以外のコミュニケーション”の重要性と、会話のコツ
- お互いの姿が見えない電話応対を、自己成長に活用する
- 社外に対する1人1人の言動が、自社のイメージに直結
- ビジネス文書やメール、社外の方との会食・慶弔事での注意点
- 最適な言葉を選んで、自分の“視線”を意識して話す
- ビジネスマナー習得のヒントは、“3つの力”
- 上司に必要なのは、「明確な指示」と「押しつけないこと」
- 自社の想いなどを盛り込んで、ビジネスマナーを学んでもらうメリット
- 会社が求めるビジネスマナーがわかれば、自分の言動に自信が持てる
- ビジネスマナーが、トラブルのない社会をつくる
- 相手や自分、会社、社会にもプラスになる“最強のツール”
ビジネスマナーは、「金銭が生じる」という点が特徴

- ――「ビジネスマナーは、ビジネスパーソンにとって不可欠なもの」ということは皆さんご存じだと思いますが、「どうして必要なのか」という理由まで答えられるひとは少ないかもしれません。私も同じなのですが、その理由を教えてください。
- ビジネスマナーと一般的なマナーは少しちがうところがあって、“ビジネス”が付くということは企業活動に必要なものなので、その言動によって「金銭が生じる」という点がとても大事です。
そして、ビジネスマナーをしっかり身につけることによって、自分自身に自信がつきますし、仕事相手の会社に対して余裕を持って対応できるようになります。
さらに、若手の方がビジネスマナーの基本を身につけていると、たとえば「若いのにしっかり挨拶や返事ができるし、いい子だな」と相手の方も安心してくださいます。
まず相手に安心感を与えて、実際に仕事をしながら信頼関係を構築していくことは、特に若い方が働いていくうえでとても重要だと考えています。
“心をつかむマナー”が仕事を生み、個人や企業、社会を成長させる
- ――ご自身のホームページで、「心をつかむマナーで、“また会いたいひと”になる」と書かれていらっしゃいますよね。この言葉には、どのような想いが込められているのですか。
- ビジネスマナーというものは、“言動”という形では相手に見えますが、そのなかにある“気持ち”の部分までは見えにくいと思います。
ですから、たとえば初めて取引をする相手に会ったときに「私は安心ですから、信頼してください」「うちの会社、大丈夫ですよ」ということを理解してもらうために、“気持ち”を“形”で表すことが大切です。
同じ挨拶でも、気持ちがこもっていると、相手からの見え方が変わります。ですから、1つ1つの言葉と行動に心や気持ちを込めて表わすことで「自分の心を伝え、相手の心をつかむ」ことが、ビジネスマナーでは重要になります。
- ――なるほど。ほかにも「心をつかむマナーは、仕事を生み、売上を上げて、経済を動かす」という言葉も書いていらっしゃいますが、相手に「また会いたい」と思ってもらえれば、仕事につながっていくということですね。そういう意味でも、先ほどおっしゃった「金銭が生じるという意識が大切」ということでしょうか。
- はい。たとえば、まったく同じペンを同じ金額で売るお店が2軒ある場合、「店構えや店内がきれいで、店員さんの対応がいい」お店で買いたいと思う方が多いのではないでしょうか。
ということは、社員がマナーをしっかりと理解・実践している会社のほうが、「お客さまが商品を買ってくださって、会社の売上や利益が増えて、社員の給与も上がる」という好循環ができていきます。
さらに、企業の売上が上がれば支払う税金も増えるので、結果的に社会や経済に貢献することにつながります。この流れの根底にあるのは1人1人の言動なので、「ビジネスマナーは経済を動かしている」と私は考えています。
実際に、私が行ったある企業のビジネスマナー研修で、「研修後に、明らかに売上が上がった」と経営者の方がおっしゃってくださいました。研修を実施したのは会社が設立5年目のときで、それまでは「仕事さえしっかりしてくれればいい」と考えていたそうですが、更に業績を上げるためにはビジネスマナーが必要かもしれないと考え、研修を導入された際の実例です。
第一印象以上に大切な、“最後”の終わり方
- ――心や気持ちを込めたビジネスマナーが相手の心をつかんで、実際に売上増加につながったのですね。ほかに、相手との信頼関係を築くために大切なことはありますか。
- “最後”が大切だと思います。
これも実際にあった話で、あるアドバイスを求められて、それに対して相手と数回やり取りして、最後に「ありがとう」という言葉をいただきました。ですが、それっきり連絡がなくて、こちらは「実際にアドバイスの効果はあったのかな。今後の参考にしたいな」と思っていたのですが、アドバイスの結果を知ることはできませんでした。
きちんと感謝の言葉もいただきましたし、ご本人に悪気はまったくないと思いますが、「次に仕事をつなげる」「良好な人間関係を築く」という場合は、最後の最後まで気を抜かず、締めくくり方や終わり方を大切にすることが本当に大事だなと実感しました。
- ――「第一印象など、最初が大切」というイメージがビジネスマナーにありましたが、そのお話をお聞きすると、最後まできちんとやり通すことは非常に大切ですね。
- もちろん、「ほんの数秒で第一印象が決まる」と言われているので、最初の部分もとても大事です。特に、就職面接などでは第一印象が重要になりますが、やはり最後に“去り行く姿”も印象に残るので気を配る必要があります。
食事のマナーについてカフェの店長さんにお聞きしたお話で、「食べ方も大切だと思いますが、私たちが見るのは“最後のお皿やテーブルの状態”です」とおっしゃっていました。
たとえば、口をぬぐった紙ナプキンをテーブルに散らかさずにまとめて置いているお客さまは、「食べ方がきれいなひとだな」と印象に残るといいます。
ですから、ものすごく第一印象が良くても、最後にちょっと残念な終わり方をすると、最後の印象のほうが残ってしまう可能性が大きいのだなと勉強になりました。
- ――とてもわかりやすいエピソードですね。おっしゃる通り、ビジネスマナーにも同じことが言えると思います。
- 普段、仕事をしていると、“最後”の部分をついつい忘れがちになってしまうんですね。だからこそ、最後まできちんと対応きる方は、「ほかのひとができないことができる」と評価が上がっていきます。
ビジネスマナーは堅苦しくない。そこに込められた意味を、まず理解しよう

- ――「ビジネスマナーは堅苦しい」と思っていましたが、基本的な所作やコミュニケーションを大切にできれば自然に身につけられそうですね。
- そうです。堅苦しいものではなく、とにかく基本さえ覚えておけば、その場に合わせてアレンジができます。そのためにも必要なのは、ビジネスマナーという“形”に込められた“意味”をしっかり理解することです。
たとえば、お客さまを自社の会議室にお迎えしたときに、“上座・下座”というものがあります。基本的には「出入り口から遠いほうが上座」と言われていますが、もし足を怪我している方や体調が悪い方であれば、奥ではなく手前の席のほうがいい場合があります。
“上座・下座”というビジネスマナーの本来の意味としては、「相手にとって一番安心・安全で、リラックスできる場所が上座」です。そういった意味を理解していれば、相手の状況に合わせて最適な場所にご案内できます。
その際に、何も言わずにご案内すると、相手の方は「あれ?」と思われるかもしれませんが、「こういう理由で手前の席のほうがよいかと思いますが、いかがですか」と説明すればわかってくださるはずです。
- ――そうすれば、相手も「マナーができていない」とは思いませんね。
- はい。一言伝えるだけで、「マナーをわかったうえで、ちゃんと考えてくれているんだな」と相手の方もうれしいですし、自分自身もうれしいですよね。さらに、そういう社員教育をしている会社自体の評価も上がります。
ですから、決して堅苦しいものではなくて、「ただ単に形を覚えるのではなく、形に込められた意味をしっかり知っておく。そして、相手に合わせてアレンジしていく」ということが、ビジネスマナーにとって大切です。
どうして、その身だしなみが必要なのか?
- ――さまざまなカテゴリーやシチュエーションごとに、ビジネスマナーがあると思います。たとえば、身だしなみでは、どのようなことが大切ですか?
- “清潔感”と“TPO(時・場所・場面)に合わせる”という2つが大事だと考えています。そして、やはり「どうして、その身だしなみが必要なのか」という意味を理解しておく必要があります。
ビジネスマナーとしての身だしなみは、「自分たちの会社が、どう見られたいか」という考え方に基づくものです。
たとえば、「お金を取り扱う銀行員は、安心感や信頼感を持たれるスーツが基本」「アパレルショップの販売員は、自社商品をきれいに着こなしてブランドに興味を持ってもらう」など、それぞれの組織や企業のイメージに合った身だしなみが求められます。
一般企業の場合も、企業側が「自分たちはどういう理念で動いていて、どんなふうにクライアントさんから見られたいのか」ということを明確にして、それに合わせて自社の身だしなみを決めていくことがとても大切です。
- ――会社側が基準を決めてくれないと、社員の方もどうすればいいかわからないので、会社から求められるものとはちがう身だしなみになってしまいますね。
- そうなんです。社員の方から「どうして、この身だしなみなのか?」と聞かれたときに、「うちの会社はこういう企業理念があって、これからこういうことをやっていきたい。そして、クライアントさんはこういう方が多いので、この身だしなみに決めている」としっかりと伝えてあげると、社員の方も納得できて、自分の身だしなみについて考えやすいと思います。
“言葉以外のコミュニケーション”の重要性と、会話のコツ
- ――コミュニケーションで必要なことを教えてください。
- ビジネスにおいて非常に大切なコミュニケーションのひとつに“言葉以外のコミュニケーション”があります。
ひとは、もし相手が“言っていること”と“やっていること”がバラバラだったら、“やっていること”のほうを信じてしまう傾向があります。たとえば、「今日はよろしくお願いします」と言っていても、投げやりな態度や表情だと「やる気あるのかな?」と思われてしまうでしょう。
言葉ももちろん大事ですが、言葉以外のコミュニケーションこそ、相手の印象に残ります。ですから、言葉以外の部分を大切にしながら、言葉と行動をしっかりと合わせることが必要です。
- ――ビジネス上の話し方や聞き方で、気をつけるべきことは何ですか?
- 「しっかり相手に伝わるように話す」ことです。たとえば、声の大きさや抑揚のつけ方、目線の送り方などに気をつけて、相手に理解してもらえるような言葉を使いましょう。もし、声が小さすぎたり、むずかしい業界用語ばかり使っていたりすると、相手は聞くのも嫌になってくるかもしれません。
聞き方として大切なのは「相手が話しやすいように聞く」ことです。たとえば、話にうなずいたり、相づちを打ったり、「それからどうなったんですか?」と合いの手をタイミングよくはさんだりして、相手が話しやすい状態をつくると、自分が聞きたいことも聞き出しやすくなります。
お互いの姿が見えない電話応対を、自己成長に活用する

- ――こちらの姿が相手に見えない電話応対では、どうすればよいでしょうか。
- まずは、「第一声を、ゆっくりはっきり言う」ことが大事です。
たとえば、自分から電話をかけた場合、普段言い慣れている自社名や自分の名前は早口でサラっと言ってしまいがちです。でも、相手は初めて聞く名前かもしれませんから、聞き取れずに「え?何ですか?」と聞き直す必要が生じて、お互いに時間を無駄にしてしまいます。
声のトーンについては、電話やたくさんの人前でしゃべるときの第一声は、“ソ”の音階にすることをお勧めしています。絶対音感の“ソ”ではなく、自分が普段話すときの音階を“ド”だとすると、そこからドレミファソと音階を上げた“ソ”の高さで話し始めると明るい印象を与えられます。
また、日本語の特徴として、普通に話していると声の高さが徐々に下がっていきやすいので、第一声のトーンを高めにすると、そのあとも話が聞き取りやすくなります。
さらに、自分が伝えたい言葉や相手の印象に残したい言葉も、トーンを上げると効果的です。これは、お互いが見えない電話でも有効ですし、プレゼンテーションなどでも活用できます。
- ――電話応対での“話の内容”についてのポイントはありますか。
- 「相手が聞きたいことを先回りして伝えて、なるべく相手が質問しなくて済むようにする」ことです。
たとえば、お客様から「○○さんはいらっしゃいますか?」という電話がかかってきたとします。そのときに、「申し訳ございません、外出中です」「何時頃に戻られますか?」「14時くらいだと思います」といったやり取りをするよりも、「ただいま外出中で、14時くらいに戻ると思いますので、もしよろしければ戻り次第ご連絡いたしましょうか?」と1回で答えれば、お互いのやり取りの手間や時間が減らせます。
そのように、「何のために電話をかけてきたのか」「どんな答えが求められているのか」ということを考えて、先に伝えられるといいですね。
- ――新入社員はまず電話応対の業務を任されることが多いと思いますが、電話応対に慣れるためのアドバイスを教えてください。
- とにかく、「怖がらずに電話を取る」こと、そして「失敗を恐れない」ことです。
最近の若い方は、プライベートで自分の携帯電話以外の電話を取ることはほとんどないと思います。また、電話番号を携帯電話に登録していれば、誰からの着信かわかるので安心して電話に出られますよね。
ですが、会社の電話は、誰から電話がかかってくるかわかりません。しかし不安がらず、とにかく電話に出て、失敗を恐れずに話すことが大事です。
率先して電話に出ることには、さまざまなメリットがあります。たとえば、電話相手が「○○さんをお願いします」と言ったら、「このクライアントさんは、○○さんが担当しているんだな」と自社の仕事の流れが少しわかってきます。
そして、いつも外線や内線の電話に出ていると、相手の方に名前を覚えていただけます。そうすると、電話を全然取らないひとに比べて「△△さんは、いつもがんばっている」と評価されますし、自分の電話応対のスキルも自然に上がっていきます。
- ――「失敗したらどうしよう」という不安を払しょくするには、どうすればいいですか。
- 失敗は誰にでもあることなので、若手のうちにどんどん失敗したらいいと思います。
若手が電話応対で少し失敗したくらいで、会社の存続の危機につながるようなことはないはずです。完璧にできなくても、どんどん電話を取って、名前を覚えていただいて、失敗したら改善しながらPDCAサイクルを回していくことで電話応対や会話の能力が上がっていきます。
社外に対する1人1人の言動が、自社のイメージに直結

- ――電話でも対面でも、社外の方に対する“敬語”がむずかしいと思っている若手社員は多いと思います。上手に使えるようになるための秘けつはありますか?
- 敬語に苦手意識があっても、どんどん使わないと上達できません。
敬語というとむずかしいと思われがちですが、敬語のなかには尊敬語・謙譲語・丁寧語があります。丁寧語も敬語の1つなので、最初から「ご査収ください」などのむずかしい言葉を使わなくても、「ご確認いただけますか」といった丁寧語や、「ですます」調で相手に不快な思いをさせない丁寧な話し方から始めればいいと思います。
そこから始めて、「周りの先輩たちがどんな言葉を使っているか」ということを学びながら、自分自身でブラッシュアップしていけば、いずれ自然に使えるようになってきます。そのように、できることから始めていくことが上達のポイントです。
- ――敬語以外に、社外の方と対面で接する際のマナーについて大切なことはなんでしょうか。
- 来客応対でも、他社訪問でも、「自分の言動が、すべて自社のイメージに直結する」と意識することが大事です。
たとえば、お客様が会社のエントランスで待っていらっしゃるときなどに、「自分のお客様でなくても、きちんと挨拶できるか」ということだけでも、自社に対するイメージが変わります。
さらに、そのお客様が担当者に「こんなふうにご挨拶してくださって、ものすごく感じがよかったですよ」と伝えてくださると、それを聞いた担当社員も、会社としてもうれしいですよね。そして、全社員に向けて「こんなうれしいことがあった」と報告されれば、挨拶をした社員のモチベーションも上がると思います。
また、自社のロゴが入った社用車で外回りをするお仕事の方であれば、運転の仕方自体が会社のイメージにつながってしまうので注意が必要です。特に、SNSなどが普及している現在は、どんな形でマイナスイメージを拡散されるかわかりません。ですから、自分の言動が及ぼす影響を意識することはとても重要です。
- ――他社を訪問する際、訪問予定時間ちょうどにお邪魔するのか、それとも何分か前に行ったほうがいいのか悩むときがあります…。
- オンライン会議などの場合は、スタート時間ちょうどか1~2分前に入室することが一般的だと思いますが、訪問するときはもう少し早めのほうがいいと思います。
ただ、あまり早すぎると相手の方が別の仕事中かもしれませんので、約束の10分前には建物に到着して、身だしなみを整えたりして、受付に声をかけるのは3~5分前が理想です。
- ――コロナ禍を経て、オンライン会議が増えましたが、そこでのビジネスマナーを教えてください。
- まずは、相手に声がきちんと聞こえて、表情がわかるような顔の映り方がするように準備しておくことが必須です。服装は、ある程度、ビジネスシーンに合ったものをお勧めします。
- ――パソコンやモニターの位置の影響で、どうしてもカメラ側に顔を向けられず、横顔の状態で話すケースもあると思います。これはビジネスマナーとして問題はありますか?
- 基本的には、「画面上で正面を向いている」形にしたほうがいいと思います。対面で直接お話ししているときに横を向いて話しているのは、相手にとって気分の良いものではないのと同様に、オンラインでも相手に不快感を与えないようにすることが大切です。
- ――コロナ禍以降、ビジネスマナーもいろいろな面で変わってきていますね。
- そうですね。コロナ禍のときは、マスクの色についてもよくご質問をいただきました。私は、ビジネスの場では黒色は印象がよくないかもしれないので、無難な白色がいいと考えています。
ビジネスマナーとは、「どの程度ならば無難か」という基準ラインを示すものでもあります。ですから、まずは無難なところから始めて、たとえば訪問先企業で女性がピンクやベージュのマスクをしていれば、自分も色を多少変えていってもいいかもしれません。
ビジネス文書やメール、社外の方との会食・慶弔事での注意点

- ――特に若手のうちは、社内や社外向けのビジネス文書を書くことがむずかしいと感じることが多いと思います。どのような点に注意すればいいですか。
- とにかく、「相手にわかるように伝える」ことです。社内文書の場合はフォーマットが決まっていることが多いので、それに沿って、装飾した言葉などを使わずに「伝えたいことをわかりやすく伝える」とよいでしょう。
社外文書には2種類あって、1つ目の請求書や領収書などは定型で作成すれば問題ありませんが、もう1つの儀礼的な文書を書く際は気をつける必要があります。たとえば、新社屋完成時や社外向けイベントなどの招待状などは、一般的な形式や自社のフォーマットを守って、礼儀も踏まえて書かなければいけません。
- ――いまは、社外の方とのメールでのやり取りが一般的になっていますが、気をつけるべきことを教えてください。
- ビジネス文書と同じように、基本フォーマットに沿って、読みやすい文章を心がければ問題ないと思います。
たとえば、最初に相手の会社名と名前を書いて、「いつもお世話になっております」などのあいさつの後、自分の会社名と名前を記し、内容を丁寧にわかりやすく書いたあとに「今後ともよろしくお願いいたします」などと締めて、最後に署名を入れれば、ビジネスマナーとしては問題ありません。
そして、いろいろな方とメールのやり取りをしているうちに、「このひとの文面はすごいな」と思ったらどんどん真似をするのが、上達するための一番の近道です。「もっとうまく書きたい」という気持ちを持って、ひとから1つ1つ学んでいくことが大事です。
- ――話し言葉と書き言葉の敬語の使い分けや、たとえば「御社と貴社」といったちがいなどで迷う方もいると思います。
- 敬語については、しっかりと学んで、どんどん使っていくことが上達のポイントです。また、文章の語尾が「思います」ばかり続いていて、それ以外の言葉が思いつかないときなどは、
ChatGPT などのAIを利用するのも1つの方法です。そして、自動生成された文章を自分でアレンジしたり、自分らしさを入れたりしていくうちに上達していくでしょう。
- ――社外の方と会食をする際は、どのような振る舞いをすればいいでしょうか。
- 基本的に、「仕事上での会食は、料理を楽しむものではなくて、会話がメイン」ということを頭に入れておいたほうがいいと思います。
もちろん、食事を楽しむことも大切ですが、「普段とはちがう環境で話せる」という会食の良さを活かして、「親睦を深めるためにコミュニケーションを取る」「仕事の話をスムーズに進める」といった目的をはっきり持つことが大事です。
また、社内外を問わず、「ビジネス上で“無礼講”というものはない」ということは覚えておくべきでしょう。あくまでも、お互いに節度を持って楽しんで、気を緩ませ過ぎないようにしたほうがいいですね。
- ――葬儀や結婚式など、慶弔事の場合はいかがですか?
- 「TPOに合った行動をする」ことです。たとえば、社外の方の葬儀でも「葬儀場で行う」「社葬にする」「ホテルなどで偲ぶ会を行う」などいろいろなケースがありますから、TPOをしっかり考えて行動することが大切です。
最適な言葉を選んで、自分の“視線”を意識して話す
- ――ビジネスシーンにおける言葉選びや表現方法について教えてください。
- “言葉の印象”が“そのひとの印象”になりますから、言葉選びは非常に重要です。たとえば、ものすごく優しい性格のひとでも、言葉遣いが乱暴だったら「乱暴なひと」という印象を与えてしまいます。そして、「そのひとの印象は、そのひとが勤める会社の印象につながっていく」ということも認識しておきましょう。
言葉を選ぶ際、たとえば新入社員の方で敬語に慣れていなくても、丁寧語で相手に敬意を払って話せば、少しくらい言葉を選び間違えても怒る方はおそらくいないと思います。電話応対と同様に、「怖がらない」ことが大切です。
- ――最近は、リーダー・マネージャー層もハラスメントを避けるために、従来よりも言葉遣いに気をつける必要が高まっていますね。
- そうですね。ちょっとした細かい言葉遣いでも、たとえば少し前までは『今日“は”キレイですね』ではなく『今日“も”キレイですね』と「は」と「も」の使い方の注意点の例で使っていましたが、いまでは「キレイですね」という言葉自体がルッキズム(外見で判断や差別すること)を排除するために使えなくなってきています。
そのように、ビジネスマナーとしての言葉選びは、さらに重要になってきていると思います。
- ――言葉以外の、身体の表現方法で気をつけるべき点はありますか。
- 腕組みや、手を後ろに組むのは、やめたほうがいいですね。そして、「話しながら体を動かさない」こともポイントです。ひとは動くものに目が行ってしまうので、聞き手に肝心な話の内容が入ってこなくなってしまいます。
逆に、「動くものに目が行く」というひとの特性を利用して、ジェスチャーをうまく活用する方法もあります。たとえば、「3つの大事なことがあります。1つ目は~」と言って指を1本ずつ増やしていくと、聞き手の気を引くことができます。そのような“意味のある動き”は有効です。
- ――複数の人前で話をするときには、どのようなことを心がければいいですか。
- “視線”がすごく大事です。
視線と声の大きさは連動しているので、たとえば大勢のひとが集まっている会場でしたら、最後列の席のひとに向かって話すつもりで第一声を出します。そうすると、「目線の先に、声は届く」と言われている通り、会場全体に声が届きます。そこから、だんだん自分の目の前に視線を移しながら話していくといいと思います。
新入社員の方などが複数の方の前で話す際は緊張すると思いますが、そういうときは“自分の話を聞きながらうなずいてくれるひと”や“ニコニコ笑いながら聞いてくれるひと”を最初に見つけるのがポイントです。
“自分の味方”を見つけることで安心し自信が持てるので、まずそのひとたちに向かって話しながら、慣れてきたら全体を見渡すと緊張せずに話せます。
ビジネスマナー習得のヒントは、“3つの力”

- ――「失敗してもいいから続ける」こと以外に、ビジネスマナーを習得するためのヒントを教えていただけますか。
- ビジネスマナーの習得には、“観察力”“想像力”“行動力”という3つの力が重要です。
まず、相手の方の状況を“観察”して、「どんなことに困っているか」を“想像”します。たとえば、先ほどお話した「相手の方が足を怪我しているな(観察)。ならば、手前の席のほうがいいかな(想像)」という流れです。
ここまではできる方が多いのですが、そのあとに“行動”に移すのがむずかしいんですね。「嫌がられたり、失礼だと怒られたりしたら、どうしよう」と思うかもしれませんが、「手前の席をお勧めする」という“行動”をして、自分が“観察”“想像”した内容をお話しすれば理解してくださると思います。
他人の気持ちというものはなかなかわからないので、「わかろうと思って行動する」ことが大切です。それを続けることによって自分の経験が増えていって、「前にこんなことがあったから、今回はこうしよう」と考えられるようになります。
- ――そのためにも、失敗を恐れずに継続することが必要なのですね。
- そうです。これは身だしなみのマナーにも通じる実話ですが、知り合いの方が学生時代に広告代理店でアルバイトをしていたときに、ほかにも何人かアルバイトがいるのに、社員が毎回自分だけをクライアント先に同行してくださったそうなんです。
その理由を聞いたところ、「君はロッカーにジャケットを置いていて、クライアント先に行くときにちゃんと着てくれるから」と言われたそうです。
広告代理店のアルバイトなので、普段はラフな服装で仕事をしていたのですが、「社員さんが出かけるとき、ジャケットを着ているな」と“観察”して、「自分も同行することがあるかもしれないから、ジャケットを用意しておこう」という“想像”して、「ジャケットを常備する」という“行動”に移したんですね。
その結果、クライアントに出向くことが多くなって、「仕事の現場で、どんな話をしているのか」ということを間近で勉強できたそうです。
このお話を聞いて、「そんなちょっとしたことが、自分のキャリアアップにつながっていくんだな」と、“観察力”“想像力”“行動力”の大切さを改めて感じました。
上司に必要なのは、「明確な指示」と「押しつけないこと」
- ――上司から部下へのハラスメントを避けるために、言葉選びと同じように、部下とのコミュニケーションの仕方に悩んでいる上司の方も多いと思います。部下に対するビジネスマナーとして、どのようなことに気をつければよいでしょうか。
- 上司から部下へのビジネスマナーに、“報告・連絡・相談(ほうれんそう)”に対して、“おひたし”という標語があります。「怒らない・否定しない・助ける・指示する」の語呂合わせですが、なかでも「明確な指示」がとても重要だと私は考えています。
部下の方が「結局、何をすればいいのかわからない」と感じる曖昧な指示や、「前に言っていたこととちがう」という一貫性のない指示などは避けるべきです。部下の方からすれば、指示が不明確だと仕事に取りかかれない状態になってしまいます。
そして、指示をするときに「押しつけない」ことも大事です。自分自身の考えや「自分はいままでこうやってきたから、君もこうしなさい」などと押しつけると、いまの時代では若い方の反感を買うおそれがあります。
指示を行う際は、「なぜ、これをしなければいけないのか」という理由や目的を必ず伝えましょう。論理的に説明すれば、納得して行動してくれます。
そういった伝え方に“正解”というものはありませんから、自分で考えて対応できる力を身につけて自分をブラッシュアップしていくことが必要です。そうでないと、上司の方が時代から置き去りにされてしまう可能性があります。
自社の想いなどを盛り込んで、ビジネスマナーを学んでもらうメリット
- ――金森さんは、どのようなビジネスマナー研修を行っていらっしゃるのですか。
- たとえば、企業向け研修の場合、3日間連続でプログラムを実施することもありますし、ビジネスマナーの全カテゴリーの講義に加えて部署ごとの業務内容にあわせた内容を重点的に行うこともあります。たとえば、「架電業務が多い部署は電話での話し方を、営業部門は他社訪問・来客対応を」といった形です。
そして、研修を行う前に、必ずその会社の考え方や課題、経営・事業の目的などをお聞きして、その内容もビジネスマナーと関連付けて研修でお話します。
たとえば、「会社の規模はまだ小さいけれども、将来的にはグローバルに事業を展開したいと思っている。そういう時期に入社してきた皆さん、働いている皆さんには、こういった言動が必要なんですよ」といった会社の想いなども盛り込んで伝えるんですね。
そうすることで、「研修を受講した社員の方々が、上司の話を素直に聞いてくれるようになった」という会社がたくさんあります。
そして、「『会社を存続させるために、ビジネスマナーがどれほど重要か』、『ビジネスマナーをしっかり行うことで、自分の評価も上がって、会社の評価や売上が上がって会社が成長していく』ということを、新入社員の時点で理解してもらえてよかった」と感謝していただくことも多いです。
- ――会社にとっても、新入社員などが入社間もないうちからビジネスマナーやその重要性を学ぶことが有効なのですね。
- そうです。そして、特に新入社員のうちは、最初からむずかしいことをやろうとするのではなく、「挨拶や返事をする」といった段階から始めればいいと思います。「新入社員は、まずは会社を明るく元気にしてくれたらそれでいい」とよく言われるくらいですから、ビジネスマナーの基本の“形”や“意味”を理解していれば、実際のマナーは少しずつ習得していければ大丈夫です。
- ――そのように「若手が段階を踏みながら学んでいけばいい」ということを上司や会社側も理解して、見守りながらサポートすることも大切ですね
- その通りです。上司の役割として「部下に仕事を覚えさせて、成果を出させる」ことはもちろん大切ですが、同じように「部下のやる気やモチベーションを上げる」ことも重要だと私は思います。
右も左もわからない状態で入社してきた若手の方を「ビジネスマナーができていない」と怒ってばかりで、何もフォローしなければ、新入社員はやる気がなくなってしまいます。
- ――ほかにも研修導入の成功事例を教えていただけますか。
- 「研修内容を踏まえて挨拶や返事をするように徹底したら、社員同士のコミュニケーションが活性化して、社内の雰囲気が変わった」という企業もあります。
また、ある大学での新入生向け研修の実施後に、学外の方から「御校の学生さんはしっかり挨拶してくれますね」「感じがいいですね」と言われることが増えて、学校自体に対する評価が高くなったという事例もあります。
会社が求めるビジネスマナーがわかれば、自分の言動に自信が持てる

- ――研修の受講者からは、どのような声がありますか?
- 架電業務を担当する新入社員向け研修を受けた方々からは、「学生時代に電話をかける業務をしたことがなくて不安だったけど、研修を受けて不安なくできるようになった」「声のトーンを上げてゆっくり第一声を発するようにしたら、相手から聞き返されなくなった」「研修を受けた翌日に、初めて成約できた」という効果をお聞きしました。
ほかの会社の研修でも「ビジネスマナーを学んだことで自分の自信につながって、堂々と行動ができるようになった」という声も多くいただいています。
- ――やはり、それだけ「具体的なビジネスマナーがわからない」という若い方が多いのですね。
- そうですね。自社が開催する研修で学ぶことで、「会社から求められているビジネスマナーがわかるので、自分が行うべきこともわかって、言動に迷いがなくなる」という成果もあります。
ほかにも、あるIT企業の事例ですと、「ビジネスマナーよりも、自分の仕事を優先したい」と考える社員が多かったそうですが、研修後は「とても勉強になったので、今後に活かしていきたい」と、前向きな意見が多く寄せられたそうです。
ビジネスマナーが、トラブルのない社会をつくる
- ――金森さんが、ビジネスマナーを通じて社会に及ぼしたい影響や、実現したい社会とはどのようなものですか?
- 社会への影響として一番大きいのは、“トラブルの予防”になることだと思います。節度を持った言動は、トラブルを未然に防ぐ効果があります。
また、謝罪会見が炎上するというケースがよくありますが、あの原因も、謝るときの言葉遣いや態度がビジネスマナーに反しているからだと思います。
たとえば、「真摯に受け止めたいと思います」という言葉は、謝っているようで実は謝罪になっていませんし、“誰もが使っている言葉”や“いろいろな解釈ができる言葉”を使うと、「真剣に謝っていない」「逃げようとしている」と非難されやすくなります。そして、トラブルがさらに拡大して、“2次災害”に発展する危険があります。
先ほど「上司が部下に指示する際の伝え方は、自分で考える必要がある」とお話ししましたが、それと同じように、
謝罪の言葉も、マナーを理解したうえで自分自身で考える必要があります。
- ――ビジネスマナーの基本や本質を理解していれば、そういったトラブルも防げるのですね。
- はい。社会全体で、みんながマナーを持って行動することによって、トラブルは減っていくはずです。また、日本社会のなかだけでなく、国際社会においても、ビジネスマナーを学ぶことは役立つと考えています。
私は海外からの留学生の方々にも、日本語学校などでは学べない“日本特有のビジネスマナー”をお教えしています。そこで、「日本では、“腕組みをして相手の話を聞く”ことはビジネスマナーとして失礼になる」と説明したら、ある国の方が「自分の国では、小さいときから『目上のひとと話すときは、ちゃんと体の前で腕を組みなさい』と習った」とおっしゃったんですね。
見え方は真逆ですが、どちらのマナーも“相手に嫌な思いをさせず、敬う気持ちが根底にある行動”です。このように、自分が仕事で関わる国のビジネスマナーや習慣など多様な文化を知って、グローバルな視点で物事を見る力や適応力を身につけることは、今後ますます重要になってくると思います。
そして、日本のビジネスマナーに込められた意味を海外の方にきちんと説明できる“マナー力”が身につけば、トラブルも起きませんし、国際社会に対しても影響力を持てる人材になることができるでしょう。そうした視点を持って行動できる人が増えるよう、伝え続けていきたいと思います。
相手や自分、会社、社会にもプラスになる“最強のツール”

- ――今年入社したばかりの新入社員の方々にアドバイスやエールをいただけますか。若手育成をする上司の方にもとっても役立つと思いますので、よろしくお願いいたします。
- ビジネスマナーというものは、自分自身にとっても相手にとってもプラスになる“最強のツール”だと思います。ですから、「堅苦しい」「よくわからない」と苦手意識を持つのではなく、ビジネスマナーを自分の“味方”と考えてほしいですね。
- ――なるほど。金森さんご自身にとって、ビジネスマナーとはどういうものですか?
- いまお話したような“相手にも、自分にも、会社にも、社会にもプラスになって、争いなく楽しく過ごすための最強のツール”です。ですから、皆さんも、覚えて使って損はないと思います。
あつしな・るせ
- 金森たかこ(かなもり たかこ)
- office T 代表 ハウス食品人事部にて人材育成・秘書業務を経験後、フリーアナウンサーとして独立。培ったコミュニケーションスキルを活かし、ビジネスマナー講師として企業、学校、病院、行政機関などで講演・研修・コンサルティングを行う。マナーとコミュニケーション能力向上を軸に、ボイストレーニングや話し方メソッドを組み込んだ独自のプログラムが好評で、受講者の成長や変化は多くの企業から高く評価されている。 クイズ番組の問題作成・監修を手掛けるなど、幅広い分野で活躍中。 監修本『ひとめでわかるモノの言い方』を含む4冊 を出版し、累計13万部を突破。 現在『日刊ゲンダイ』にて 「ビジネスマナー常識チェック」を連載中。



