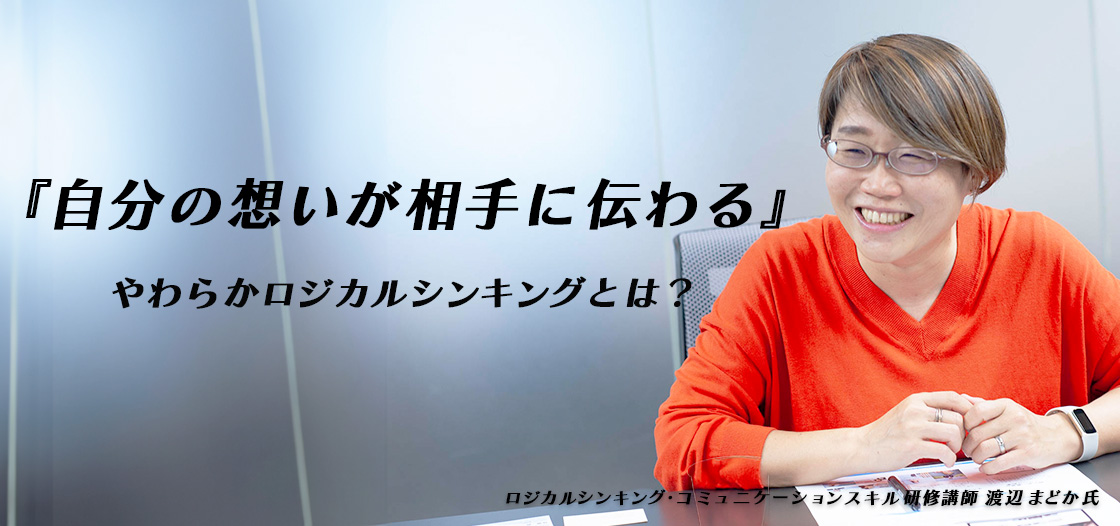 ロジカルシンキング・コミュニケーションスキル研修講師 渡辺まどか氏
ロジカルシンキング・コミュニケーションスキル研修講師 渡辺まどか氏この記事はプロモーションが含まれていることがあります。
今回は、誰もが取り入れられる『やわらかロジカルシンキング(やわロジ)』を提唱し、多くのビジネスパーソンや企業にロジカルシンキングを伝授している渡辺まどか氏にインタビュー。ロジカルシンキングの基本や応用、そして活用するために重要な“想い”を持つ意味など、激動の時代を生き抜く考え方やコミュニケーション術、キャリアスキルなどのヒントにしてほしい。
目次
- 自分の“想い”を伝えるためのツール=ロジカルシンキング
- 一握りのひとだけでなく、誰にでも役立つ『やわらかロジカルシンキング』を
- “伝える”ための4つのステップ。まず、相手のことを知る
- 相手に合わせた切り口と、プレゼン成功のための2パターン
- “雲”“雨”“傘”で、本当に伝えたいことが正しく伝わる
- 上司・部下間のコミュニケーションへの応用
- ひとが“やりたいこと”に、優劣はない
- “言わされていること”ではなく、個人と企業の想いが重なる部分を大切に
- プレゼン設計のヒントは、自分で言語化できていない背景を自覚すること
- 企業が社員にロジカルシンキングを習得させる効果と成功事例
- 一人一人の個性によって、最適なトレーニング方法がある
- “一人一人が、自分らしく生きられる”ロジカルシンキングを、社会に広めたい
自分の“想い”を伝えるためのツール=ロジカルシンキング

- ――最初に、ロジカルシンキングとはどういうものかを教えてください。
- 一般的にロジカルシンキングとは、いい意味でも悪い意味でも、「論理的に考えて伝える」ための“ツール(道具)”です。良いツールを持っていることで、自分がやりたいことや“想い”が伝わりやすくなります。だからといって、このツールさえあればすべてが解決できる〈魔法の杖〉ではありません。
そして、ロジカルシンキングと言うと「むずかしいもの」と捉えられがちですが、私自身は「そんなに突き詰めなくてもいい」と思っています。どんなにロジカルシンキングという“技術”を磨いても、ロジカルな考え方ができるひとでも、「自分が伝えたいことが、うまく言葉にできない」という方はいらっしゃいます。
ですから、私はむしろ、“技術”よりも“想い”を持つことのほうが大切だと考えています。
- ――それが、渡辺さんが提唱していらっしゃる『やわらかロジカルシンキング』ですね。
- そうです。一般的なロジカルシンキングは、技術の部分だけをフィーチャーしているものがほとんどですが、私はそれだけではあまり意味がないと思っています。
あくまでも、ロジカルシンキングは、伝えるための“How(=方法)”で、コミュニケーション能力の一つです。その技術と、自分が「これをやりたい」「こうありたい」という想いが合わさってこそ、最大限の力を発揮すると考えています。
一握りのひとだけでなく、誰にでも役立つ『やわらかロジカルシンキング』を

- ――先ほどおっしゃられた通り、ロジカルシンキングは「習得が簡単ではない」というイメージがあります。そのなかで、渡辺さんの『やわらかロジカルシンキング』は非常にわかりやすく、初心者でも取り組みやすそうだなと感じました。
- 「ロジカルシンキングは、優秀なビジネスパーソンのための特別な技術」と考える方も多いかもしれませんが、私はそうは思いません。
さまざまなロジカルシンキング関連の書籍がありますが、読んでいて「自分が実践できるのかな……」と感じるものもあります。せっかく良い思考法でも、理解するのがむずかしくてはもったいないですよね。
私自身もロジカルシンキングの講師を始めた当初は、ロジカルシンキングを“真面目に取り組むべきもの”だと捉えていました。しかし、「むずかしい」とおっしゃるセミナー・研修受講者の方が多かったので、日常的なコミュニケーションで使える実用的なものを考えました。
「もっとたくさんのひとが、すっきりと自分が言いたいことを伝えられるようになったらいいな」と思って、最低限のポイントを押さえるだけで簡単にできるように考えたのが『やわらかロジカルシンキング』です。
- ――どのようなひとが、渡辺さんのセミナーや研修を受講していますか?
- 大企業で企画などに携わっている方々ばかりではなく、たとえば看護師の方や新入社員の方など、さまざまな方がいらっしゃいます。
目的はひとによって異なりますが、皆さんに共通しているのは、「コミュニケーションがうまくできないけれども、この職場でがんばりたい」「こういう仕事をやりたいから、できるようになりたい」という気持ちです。
- ――ビジネスのための技術の習得という目的だけでなく、そういった想いを持っている方も多いのですね。
- はい。私は、一握りのトップレベルのひとだけが使えるハイレベルなクリティカルシンキングなどではなく、そのような一生懸命働いている方々や「ひとのためになることがしたい」とがんばっている方々に役立つロジカルシンキングをお伝えしたいと考えています。
「必要以上に飾り立てるのではなく、あなた自身のままでいい。伝えたいことや言いたいことがあるというだけで、まずは大丈夫」と皆さんに安心していただいて、それぞれの想いの実現をサポートするロジカルシンキングを身につけていただきたいと思っています。私がロジカルシンキングの講師として独立したのも、そういう想いを持っていたのが最大の理由です。
自分では「自信、安心、ロジシン(ロジカルシンキング)」と呼んでいるのですが(笑)、そのようなものでありたいと考えています。
“伝える”ための4つのステップ。まず、相手のことを知る

- ――以前、渡辺さんのセミナーで、お弁当屋さんを例に挙げてロジカルシンキングについてお話していらっしゃいましたよね。そのお話について、詳しく教えていただけますか。
- 『やわらかロジカルシンキング』は、4つのステップにわかれています。1つ目は、「誰に話すか」を考えることです。
皆さんは、「何かを話さなきゃいけない」と思ったときに、いきなり話す内容を考え始めることも多いと思います。しかし、「何を話すか」よりも先に、「話す相手を具体的に思い浮かべる」ことが大切です。「そんなことは当たり前」と思うかもしれませんが、話す内容を整理するために非常に重要になります。
そして、「相手は、何に興味・関心があるのか」を考えます。お弁当屋さんであれば、たとえば「お腹が空いていて、ランチタイムは1時間しかないから早めに買って帰れるお弁当を買いたい。できれば、満足できるボリュームで、午後の活力になるものがいい」といったお客さんのイメージです。
- ――相手の興味や関心を完全に知るのはむずかしいと思いますが、どうすればよいですか?
- 表面的ではなく、できる限り“立体的”に相手を知ろうとすることが大事です。
たとえば、自分が職場の部下で、上司に何かを伝える際に、「このひとは、これまでどんなことをしてきて、何が大切だと考えて仕事をしているのか」「どんなことが好きで、何が嫌いか」といった点も含めて、相手の人物像や興味・関心の対象を知る。そして、それらがわかれば、相手の立場に立って物事を考えやすくなります。
そのためには、普段の“会話のキャッチボール”が大切です。日常的に雑談などをするなかで相手のことを知れば知るほど、「きっと、このひとだったら、こういうことに興味を持つだろう」「こんなことに困っているんじゃないか」と見えてきます。そのように、話し相手について具体的にイメージできるようになることが第1ステップです。
このステップは、ロジカルシンキング全体において非常に重要だと思います。
相手に合わせた切り口と、プレゼン成功のための2パターン

- ――相手のことが見えたところで、次はどのようなステップになりますか。
- 「自分が言いたいことを伝える」のが最終目的ですが、より伝わりやすくするために「相手が知りたいことや興味があることに合わせた切り口を考える」のが第2ステップです。
たとえば、お弁当屋さんが一番伝えたいことは、「自分たちのお弁当を買ってほしい」ということです。しかし、ただ「買ってください。何円です」とだけ言っても、相手の心に響きませんよね。
そこで、先ほどお話ししたようなお客さんの興味・関心に対して、たとえば「食べると、すごく幸せな気持ちになれます!」といったキャッチフレーズで販売します。そうすると、「これを食べたら、午後も元気に働けるかも」と思って買ってくれる可能性が高まります。
- ――相手のニーズや心理に訴える切り口が大切なのですね。
- 私たちが普段話すときは、「自分が言いたいことを、言いたい切り口と順番で、言いたいように話してしまう」というのが、ごく普通だと思います。そのため、うまく伝わらないこともあるんですね。
もちろん、「自分が言いたいことを言う」のが大切で一番の目的ですが、相手にうまく伝えるには、相手の状態や興味・関心に合わせた切り口に焦点を当てないと“刺さらない”と思います。
そして、第3ステップが、「相手が知りたいことや興味・関心を満たすために、何を押さえなければいけないか」を考えることです。
- ――自分本位ではなく、相手が「なるほど」と納得するポイントをつくわけですね。相手のタイプなどによってさまざまな可能性が考えられて、最適なポイントを見つけるのは簡単ではなさそうですが、良い方法はありますか。
- 本来であれば、相手が納得するために外せないポイントやその順番を精査するべきなのですが、「これを覚えれば、大体5~ 6割のケースに通用する」という2つの方法を私はお勧めしています。
1つめが、いわゆる“問題解決”と言われるものです。「いま抱えている問題を特定して、その原因が何で、それに対する対応策を考えて、最後に『誰がいつまでに行う』といったアクションプランを立てる」というパターンです。この方法は、トラブル対応だけでなく、相手に提案したいときにも活用できます。
これは、通販番組などにも使われているフォーマットでもあります。最初から単に「買ってください」とお願いするのではなく、「こんなことで悩んでいませんか?」→「そのお悩みの原因って、実はこれなんです」→「そのお悩みを解決するのが、私たちの商品です」とつなげるのが王道です。
さらに、「これから30分間、オペレーターを増員してお待ちしております」と続けて、「電話をかけて購入して、手元に届いたら使用するだけ」というアクションプランを提案するわけですね。この“問題解決”パターンを覚えると、ちょっとしたプレゼンであればかなり成功率が上がると思います。
- ――なるほど。たしかに、話の設計が簡単そうです。
- そして、2つめが、「こうすべき」と訴えたいときに活用できる「○○すべきか、否か」というフォーマットパターンです。メリットとデメリットを整理して、「メリットがデメリットを上回る、行うべき」「さらにこのメリットを得る代替手段がほかにないから、これ以外の方法はない」と提案します。
「相手が何を知りたいか。興味があるか」というポイントを押さえたうえで、この2つのパターンのどちらかを使うと、かなり多くのケースに対応できると思います。
さらに、最後の第4ステップは、ここまでの3ステップに沿って“自分が伝えたい”ことをまとめる工程です。この4つのステップを実践すると、相手のニーズに合う形で自分が言いたいことが整理されていくので、伝わりやすくなります。
“雲”“雨”“傘”で、本当に伝えたいことが正しく伝わる

- ――4つのステップに加えて、伝える内容の筋道を立てて説得力を持たせる方法はありますか?
- 私の拙著『図解でわかる! ロジカルシンキング』でも触れている“雲”“雨”“傘”という考え方を使うと、相手の納得感が高まると思います。
“雲”とは「空に雲が出ている」と、誰もが目で見て確認できる“事実”です。その事実(=雲)を踏まえて、「雲が出ているから、雨が降りそうだ」といった、そのひとなりの“推測・解釈”が“雨”になります。そして、その推測・解釈を踏まえて、「傘を持っていこう」など「どうするか・どうすべきか」という判断や提案が“傘”です。
この3つのなかで、事実である“雲”の部分以外の“雨”“傘”の内容は、ひとによってちがってきます。3つすべてが大切なのですが、私たちがコミュニケーションする際、この3つを切り分けて考えていないことが多いんですね。混在してしまっていて相手にわかりにくかったり、3つのうちの1つしか伝えていなかったりということも珍しくありません。
- ――この3つが揃って初めて、本当に伝えたいことが正しく伝わるのですね。
- その通りです。これら3つをセットにして伝えることができれば、お互いのコミュニケーションも改善されて、建設的でわかりやすくなります。
たとえば、子どもが「お母さん、お腹が空いた」と言ってきたとします。その場合、「お腹が空いた」という子どもの状態が“雲”(=事実)です。でも、「ごはんの時間には早いし、お母さんはまだごはんをつくっていないだろう」と、子どもは推測・解釈している可能性があります。
そして、子どもが本当に言いたいことは、「ごはんの前に、おやつがほしい」という提案(=“傘”)かもしれません。しかし、子どもは“雲”の部分しか言っていないので、本当に求めるものが伝わってこないんですね。
- ――同じようなケースは、職場でもありそうです。
- そうですよね。たとえば、「パソコンの状態がおかしい」とだけ伝えて、「見てみてほしい」「直してほしい」といった“本当に言いたいこと”が抜けがちになるケースはよくあるはずです。
上司・部下間のコミュニケーションへの応用

- ――職場でのコミュニケーションについて、ハラスメントを恐れて、若手への対応にむずかしさを感じている上司が多いと思います。特に、「部下からの提案に対して、どう対応すればいいか」と悩んでいるひとも多いようです。そのような課題に対する、『やわらかロジカルシンキング』の活用方法を教えてください。
- たとえば、上司の方にとっては「とんでもない」と思えるような提案を、メンバーの方が持ってくることがあるかもしれません。でも、その背景には、部下の方なりの捉え方や考え方があるはずです。
それを聞かずに、いきなり否定してしまうと、そのひと独自の個性や感性、思考を潰してしまうことにつながります。そして、その時点で、やる気を失わせてしまう可能性があります。
そうならないためには、“傘”であるアウトプット部分だけを見て頭ごなしに自分の見解を伝えるのではなく、その根拠になった“雲”と“雨”もきちんとヒアリングすることが重要です。さらに、自分が相手に伝える際も、自分自身の“雲”“雨”“傘”を揃えることで、部下の方の納得度を高められます。
- ――逆に、部下の立場として、上司から一方的に「これはちがうから、変更して」と言われて困惑するケースも多いと思います。
- 上司の方が「この書類、間違っているから直して」「その考え方は正しくないから、再考して」と、“傘”(提案)だけを伝えるケースはよく見られます。
そうすると、部下の方としては「間違ってなんかいないですよ!」と反発したり、「間違ってるんだ、すごく恥ずかしい。ショックで、これ以上何も言えない……」という委縮状態になったりしてしまいます。
この2つの反応は真逆に見えますが、どちらの本質も同じで、部下側が「相手が言ったことは、どういうことなのか」という部分を突っ込んでいないが故の行動です。
- ――これも、コミュニケーションのキャッチボールができていないことが原因なのですね。
- 「相手が言ったことは、こういう意味だ」と、自分で勝手に解釈してしまっているんですね。
たいていの場合、上司の方は別に怒っているわけではなくて、「あなたの言いたいことがわからない」「内容にちょっと違和感がある」のだと思います。ですから、部下の方は「『間違っているから直せ』という“傘”に至った“雲”“雨”は何か?」を解き明かすような質問をすることが大切です。
そうすれば、上司の方から「過去の事例と照らし合わせると、こういう場合はこんな結果になることが多かった、だから、私の判断では君が書いた内容は間違っていると思った」という理由や考えを聞くことができます。
その答えに対して、「私は過去の事例を知らなかったので、その事例を教えていただけますか」といったコミュニケーションができれば、その後の状況がまったく変わってきますよね。
そして、部下の方自身の学びになるのと同時に、上司も「次は、より改善されたものが出てくるだろう」と期待を寄せてくれて、さらなる自己成長やキャリア形成につながると思います。
ひとが“やりたいこと”に、優劣はない

- ――「ロジカルシンキングという“技術”よりも、“想い”が大切」というお話がありましたが、やりたいことや伝えたいことが特にないというひともいるのではないでしょうか。
- たしかに、私の講座を受けてくださる方のなかにも、そういう方は少なくありません。でも、「いまの仕事を選んだ」「辞めずに、やり続けている」ということは、そこになんらかの意味があるはずです。その意味をご自身がわかっていらっしゃらなかったり、言語化できていなかったりするだけだと思います。
「ロジカルシンキングは、“やりたいこと”(=想い)が大切」というお話をすると、皆さん「何か“すごいこと”でなければいけない」と考えて、「そんなものは、ないです」とおっしゃるんですね。でも、私は「“やりたいこと”に、優劣などの区別はない」と思います。
私がご相談を受けるケースのなかで、「管理職前研修でロジカルシンキングのプログラムがあって、うまくできなくて困っている」という40歳前後の方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、内容をよく聞いてみると、ロジカルシンキングという技術的な部分よりも、「どういう想いや志を持って、組織を動かしてるか」「どういう組織にしていきたいと思っているのか」という“想い”の部分を言語化することを問われているんですね。そこで、「それは、皆さんが普段やってることや、やりたいと思っていることなので、それをわかりやすく伝えればいい」とお伝えしています。
- ――ロジカルシンキングという文脈に無理やりはめ込んで、むずかしく考える必要はないわけですね。
- そうなんです。皆さん、ロジカルシンキングというものには“答え”があるように思ってしまって、特に研修などでは「もし合っていなかったらどうしよう」と不安を感じていらっしゃるように見えます。
そして、「自分の想いや個人的な思い入れを入れるのはよくない」と考えがちになりますが、私は個人の主観やストーリーで語ることが大切だと思います。それが、つまり、自分が“やりたいこと”なんですね。
先ほどお話したように、そこには優劣というものはなくて、「新規事業がやりたい」「組織の雰囲気をギスギスさせたくない」「非効率な業務プロセスを効率化したい」など、それぞれの“やりたいこと”があるはずです。そして、そのようなさまざまな想いを持った人がいるからこそ、結果的に組織全体がよくなるのだと思います。
“言わされていること”ではなく、個人と企業の想いが重なる部分を大切に
- ――「自分が働いている意味ややりたいことを、きちんと言語化できていない」という点に関して、どのような課題が企業や働くひとたちにあると感じていらっしゃいますか?
- 普段、私たちが口にしている言葉には、必ずしも自分が本当にやりたいわけではなくて、「やったほうがいいだろう」と感じて“言わされている”言葉がたくさんあると思います。特に、組織で働いていると「状況や方針から考えて、こうしたほうがいいかな」「上司が言っていることから逆算すると、こうすべきだろう」と考えた発言が少なくないはずです。
でも、“やりたいこと”と“言わされていること”はちがうので、そのちがいを自覚する必要があります。
私自身、コンサルティング会社で働いていたときは、“言わされていること”ばかり話していました。まだ20代の小娘だった私が、コンサルタントとして大企業の役員や事業部長、命をかけて事業の拡大や再生などに取り組んでいる方々に対して「ツールで分析した結果、御社はこういうことをするべきです」と提案していました。でも、その内容は正直、「自分自身がやりたいとは思わない」ことがほとんどだったんです。
そして、クライアント企業や社会全体に対して「こんな姿を実現したい」という私自身の想いがなく、「この提案が顧客に刺さるかどうか」ということしか考えず、小手先のロジカルシンキングの技術だけで話をしていました。
そういう状態ですから、たとえ自分自身で「いいプレゼンができた」と思ったとしても、「お客様と良好なコミュニケーションができて、信頼関係が築けている」とは感じられませんでした。だから仕事をしても手ごたえが感じられず、疲弊して最終的に退職することにしました。
いま思うと、真剣に事業や経営に取り組む方々にとって、私の話はうすっぺらく聞こえていたでしょうし、それでは信頼してもらえるはずがないなと思います。
- ――なるほど、ご自身の経験からも、“言わされていること”ではなく“やりたいこと”を大切にすることの重要性を実感されているのですね。
- はい。ひとが組織で働く際に、“自分がやりたいこと”と、組織の企業理念やミッション、バリューといった“組織がやりたいこと”が重なっている部分があるから、その方はそこで働いているのだと思います。逆に、重なる部分がなければ、転職や起業するしかないかもしれません。
ですから、「自分の思いや志が、組織と重なる部分があるかどうか」ということは非常に重要です。
- ――ロジカルシンキングを行って、良い提案をしても、重なる部分がなければ自分がやりたいことを実現するのはむずかしそうですね。
- そうです。また、組織側は働くひとたちを利用しようというわけではないのですが、普段のあり方としては「この目標を達成せよ」「これをやれ、あれをやれ」というコミュニケーションになってしまうことが多いと思います。
そうなると、働く側は「言われた通りにやればいいんでしょ」「言われた範囲内で、成果が上がればいいだろう」と、自分を殺して組織の意図に従えばいいと考えてしまいます。そして、「自分が何をやりたいか」ではなく「会社が、どうやれと言っているか」ということがすべてになってしまいます。
でも、それでは、その方が本来持っている力を一定の条件や制限のもとでしか発揮できなくしてしまいます。
上司と部下などの個人同士の関係でも同じで、重なる部分があれば、それぞれの力を発揮しながら協力してお互いがやりたいことを実現しやすくなります。
プレゼン設計のヒントは、自分で言語化できていない背景を自覚すること

- ――ほかに、渡辺さんの講座やセミナーを受けるひとたちと接していて“言語化”に関する課題感はありますか。
- たとえば、とある企業のミドル層向け企業研修で、「本当にやりたいの?」と思うような事業計画書を提出された方がいらっしゃいました。その研修では、事前課題として事業計画書の作成が課されていて、その方は太陽光発電に関する提案内容でした。内容はその方の所属組織の目標に合っているのですが、実現性や他社との差別化がむずかしいと私は感じたんですね。
でも、きっとこのひとなりの理由があると思って話を詳しく聞いてみると、地方出身の方で「すごく田舎で、町が過疎化していてすごく寂しい。どうにかして盛り上げられないかと思っている」というお話でした。
そして、事業計画書には表れていませんでしたが、「太陽光発電を通じて、地元の商工会議所や主要企業などをコラボレーションさせて、町が一体となって盛り上がる」という、“町おこし”のようなことをしたかったようなんですね。
- ――ご本人が自覚していなかったので、事業説明書にも書かれていなかったのですね。
- はい。自社に関係がある発電という切り口だけを考えた事業計画書を書かれたようでした。そのため、焦点がぼんやりしていて、突出した魅力がないように見えてしまっていたのです。
ですが、その方がそのアイデアを思いついた背景にあったのは、会社に「これをやれ」と言われたことだけではなく、ご自身が生まれ育った環境でした。
そこで、「発電のシステムを新事業としてやりたいわけではなく、発電を通じた町おこしがやりたい」という軸に振ってみたらどうですかと提案したところ、「たしかに、自分がやりたいのはそっちのほうかもしれない」とおっしゃっていました。
この事例のように、自分の想いと組織の目的・事業などが重なる部分があると、働く方それぞれが力を発揮できる可能性が高まると思います。
- ――自分がやりたいことが明確になれば、プレゼンの説得力も高まりますし、自分自身の満足度も変わりますね。お話を聞いていると、ロジカルシンキングを行ううえで、やりたいことや想いがいかに大切なのか、そして上手に伝えることが重要なのかがよくわかります。
- 自分がやりたいことというのは、「自分にとって大切で、意味がある」と思っていることなので、相手に一生懸命伝えようとしますよね。そして、もし伝わらなかったとしても諦めず、ほかの方法を考えて改めて伝えようとすると思います。そのための技術が、ロジカルシンキングなのです。
さらに、ちがう見方をすると、「自分の想いを大切にしてロジカルシンキングできるひとは、相手の想いも大切にする」ことができるという特徴があります。
たとえば、相手の意見や提案などに対して、「自分と同じように、このひとなりの意味があるだろう」と思えることで、きちんと話を聞こうとするんですね。また、表面的な解釈だけでなく、発言の背景である“雲”や“雨”を質問することで、お互いに建設的なコミュニケーションが可能になります。
どんなに技術としてのロジカルシンキングに優れていたとしても、お互いの想いを大切に考えることができなければ、コミュニケーションは成立しません。加えて、相手の想いを大切にしようという姿勢は、最終的に自分のロジカルシンキングというコミュニケーション技術の向上にも返ってきます。
企業が社員にロジカルシンキングを習得させる効果と成功事例

- ――ここまで、『やわらかロジカルシンキング』のさまざまな効果を教えていただきましたが、企業が社員に習得してもらうと、どのようなメリットがありますか?
- さまざまなメリットがありますが、一番大きいのが社内コミュニケーション、特に上司と部下のコミュニケーションでのメリットです。ダイバーシティ(多様性)への対応が企業に求められるなかで、コミュニケーションを活性化させるために役立ちます。
また、コミュニケーションスキルとキャリアスキルは一体なので、社員の方々のキャリア形成にも効果があります。
- ――単なるテクニックだけでなく、“想い”を大切にしているからこそ、ロジカルシンキングもコミュニケーションスキルも身につくのですね。これまでに導入された企業の成功事例を教えてください。
- たとえば、女性管理職候補者向けの企業研修で、ロジカルシンキングを踏まえたコミュニケーションとキャリアについてお話させていただいたときは、「管理職をやってもいいかなと思うようになりました」といった声をいただきました。そういった方が1人でも増えてくださるのは、すごくありがたいなと感じています。
また、これは逆に働く方側から見た効果事例にはなりますが、「いまの仕事がなんとなく嫌で、商品企画の仕事がやりたい」と私の個人レッスンを受けていらっしゃった方がいました。そして、受講を続けているうちに仕事上で成果が出て、商品企画を任されるようになりました。企業にとっては、このような人材の育成や教育にも役立ちます。
一人一人の個性によって、最適なトレーニング方法がある

- ――渡辺さんは、一人一人の個性に合わせたロジカルシンキングのトレーニング方法を教えていらっしゃいますよね。「どのようなひとに、どのような方法が適しているか」を教えてください。
- 一概には言えませんので、あくまでもタイプ別の傾向とトレーニング方法の一例としてお話ししますね。“雲”“雨”“傘”の考え方で言うと、「“雲”を言っておしまいにしがち」な方と、「“傘”を言うだけになりがち」な方と、「“雲と“雨”が混ざりやすい」方が多く見られます。
「“雲”だけ」の方は、客観性が比較的高くて、分析することや考えること、言葉で表現することが得意な傾向があります。たとえば、「こういう分析データが出ていて、こういう状況です」と、物事を客観的に捉えて説明することは得意なのですが、そこから一歩踏み込まないんですね。
「この解決方法が一番良さそうです」という“雨(推測・解釈)”の部分まで言っても、「だから、私はこれをやるべきだと思います」という“傘(判断・提案)”の部分まではあまり言わないことがよくあります。
そういう方は、自分の想いが相手に伝わりにくいので、「こんなに一生懸命分析したのに、どうして評価してもらえないんだ」という不満を抱え込んでしまいます。そうならないために、せっかく分析した結果を踏まえて、“雨”と“傘”の部分を重点的にトレーニングすることをお勧めします。
- ――“傘”だけのひとは、いかがでしょう。
- このタイプの方は、自分自身のなかで「それをやることが当たり前」と考えがちで、「なぜ、それをやるのか」という部分に焦点が当たりにくいのが特徴です。
「そもそも、どういう状況にあって、どうしてそれが必要だと思った」という内容を相手に説明することが必要だという意識すらない場合もあります。ですから、悪気はないのですが、「これをこういう風にやるべきです。以上」といった言い方になってしまいます。
一見行動力があって面倒見が良いので、周囲から頼りにされるのがこのタイプです。しかし、自分から積極的に行動するので、「部下が育たない」「部下がついていけず、疲れて潰れてしまう」ということが起きます。
“傘”だけの方に推奨しているのは、「そもそも」という言葉を使うことです。実際、このタイプの方は、「そもそも」という言葉を全然使わない傾向が強くあります。「そもそも」という言葉は、自分が考えたことの前段階に焦点を当てる言葉です。ですから、「そもそも」と言ったり考えたりすることで、“傘”に至った“雲”と“雨”に意識を向けやすくなります。
- ――普段はあまり気にしていない部分を掘り下げてみて、そのプロセスも伝えることで、相手も理解や行動がしやすくなるのですね。もう1つの、“雲と“雨”が混ざりやすいというのは、どのようなひとでしょうか。
- 「こうあるべき」「こういう状態にありたい」という理想の姿を描くことができて、それを実現するために「活用できるものは、何でも使おう」という発想ができる方によく見られるのが、この傾向です。
「『白か黒か』をはっきりさせなくても、白も黒も使えるよね」という考え方なので、いろいろなひとを巻き込みながら物事をあるべき姿に持っていく力がある一方で、本人にとって「それが事実であるか、事実でないか」ということはあまり重要ではないんですね。
- ――事実と自分の推測・解釈がごちゃごちゃになってしまうのですね。
- ですから、「事実ではないことを、事実であるかのように捉えてしまう」ことや、逆に「事実だけれども、都合の悪いところに関しては認識しない」ということが発生しやすくなります。相手側としては「言っていることはよく理解できていなくても、自然に巻き込まれている」というケースが多くて、組織のリーダークラスに割と見られるタイプです。
この傾向がある方は“雲と“雨”を分けて考えることが苦手な方が多いので、ロジカルシンキングの先生としては教え方に困るのですが(笑)、自分の考えのもとになる“雲と“雨”の部分を私と一緒に考えながら、自分自身で気づいていただいて進めていくことが多いですね。
“一人一人が、自分らしく生きられる”ロジカルシンキングを、社会に広めたい

- ――今後、『やわらかロジカルシンキング』を通じて、どのようなことを実現したいとお考えですか?
- まずは、一握りのひとだけにしか使えないロジカルシンキングではなく、“普通に生活して、普通にがんばっている”ひとたちが「自分が持っている想いで大丈夫なんだ」と思えて、自信に少しでもつながるようなロジカルシンキングをお伝えしていきたいと考えています。
そういうひとが増えれば増えるほど、「私は、これがやりたい。こんなふうにしたい」と考えて、実際にそれを実行して自分の価値や力を発揮するひとも世の中に増えていくと思います。
それは、“一人一人が、自分らしく生きる”ことと同義ですし、“自分らしく生きて、自分らしい発信をする”ことが、結果的に社会にとって多様な価値をもたらす可能性があります。そのなかで大きなイノベーションや、日本の社会課題解決の方法が生まれるかもしれません。
「日本は同調圧力が強い」とよく言われますが、「自分がやりたいことを実現するには、どうやって周りと関わればいいだろうか」と考えるひとがたくさん育っていけば、より多様な価値が発揮される社会になるはずです。
その“母数”になるひとが少ない社会では、育つ人材も育ちませんから、裾野を少しでも広げていきたいと思っています。
- ――そのためにも、誰もが「自分らしく、自分の“想い”を伝えられる」ロジカルシンキングが必要なのですね。
- そうです。そして、最終的に“とんがった、すごい人材”になる必要もないと私は考えています。むしろ、「自分はこういうことがやりたいので、こんなふうに実現したい」という自立した想いを持つひとが集まった組織のほうが、みんなが自律的かつ主体的に動くので、すごく盛り上がる組織になると思っています。
そして、「楽しく働ける」「熱中して働ける」「安心して働ける」といった企業環境や社会が生まれるとも思います。
ここで言う“安心”というのは、「雇用が保障されている」ということだけではなく、「飾らない自分の想いと、それを伝えるために必要な技術があれば、周囲の役に立ったり貢献できたりするんだ」という安心感も含まれています。そんな企業や社会になっていけばいいなと考えています。
- ――最近は、企業でのエンゲージメントや心理的安全性が企業の急務になっていますが、そういった部分にも『やわらかロジカルシンキング』の手法が役立ちそうです。もはや、“ロジカルシンキング”というジャンルを超えているような気がします。
- そうですね(笑)。私自身は、「自分の想いを言葉にする」ための方法だと考えています。単なるテクニックではなく“想い”も重視しているので、ダイバーシティやキャリア形成、人材開発、コミュニケーションなど、企業課題を解決するためにも効果的です。
短期的な効果もありますが、中長期的視点に立った人材育成をはじめ、社員がイキイキと働ける環境づくり、自主性の醸成などの企業戦略にも役立つので、『やわらかロジカルシンキング』のような“誰もが使える考え方”をさらに広めていきたいと思います。

文/あつしな・るせ
写真/大井成義
- 渡辺まどか(わたなべ まどか)
- 東京大学文学部卒業、日本コーチ連盟コーチングファシリテーター、ロジカルシンキング・コミュニケーションスキル講師 SEを経てコンサルティング会社で事業戦略の立案、業務改善などに従事する傍ら、人材育成にも携わる。退職後は研修講師として独立。コミュニケーション、ダイバーシティ、キャリア等の企業研修のほか、スキルシェアサービス「ストアカ」で延べ1200人以上にロジカルシンキング講座を実施。ツールとしてのロジカルシンキング+自分の本当の思いを言葉にすることで社会に貢献する人を増やすことをミッションとして活動中。著書に「図解でわかる!ロジカルシンキング」「シート1枚で論理的に伝える技術」(共に秀和システム)がある。



